パソコン版のウェブサイトを表示中です。
(広報誌「地震本部ニュース」令和6年(2024年)冬号)
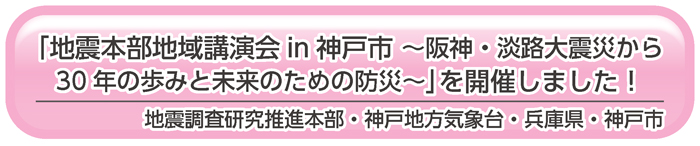

令和7年1月17日で、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災の発生から30年を迎えます。阪神・淡路大震災では、観測史上初めて震度7を記録し、6,434名もの尊い命が失われる大きな被害が発生しました。この震災で、地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当する機関に十分に伝達され活用されていなかった反省が、地震調査研究推進本部(以下「地震本部」という。)設立の契機となりました。
地域住民の一人一人が、阪神・淡路大震災の教訓や、兵庫県周辺で発生する地震の特徴、このような地震災害に対する政府の取組を知り、改めて災害への備えを考え、見直していただくことを目的として、地震本部、神戸地方気象台、兵庫県、神戸市が連携して、令和6年12月8日、兵庫県神戸市で「地震本部地域講演会 in 神戸市 ~阪神・淡路大震災から30年の歩みと未来のための防災~」を開催しました。
開会に当たり、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課の吉田和久地震火山室長から、冒頭挨拶をいたしました。
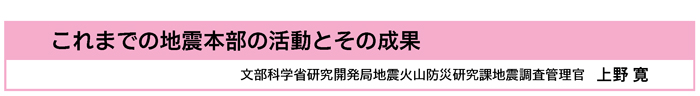
初めに、地震本部の事務局を務める上野地震調査管理官から地震本部の取組について説明しました。阪神・淡路大震災を契機に地震本部が設置されたことに触れるとともに、地震本部の役割や組織構成を説明し、緊急地震速報、地震動予測地図、活断層の長期評価といった地震本部の成果を紹介しました。地震動予測地図の説明では、近畿地方の確率論的地震動予測地図を例に、地震動予測地図の作成方法や、確率の捉え方について解説しました。また、J-SHIS「地震ハザードステーション」内の地震動予測地図を用いて、講演会会場における地震ハザードを確認しました。

岩田名誉教授からは、阪神・淡路大震災において大きな被害が発生した「震災の帯」の成因に触れ、丘陵地と平地の境にある活断層位置より平地側において揺れが増幅することを解説いただきました。丘陵地と平地境界の至る所に活断層がある近畿地方では、大きな揺れが発生する条件に合致する箇所が多くあることから、平地側で大きな被害が生じ得ることを説明いただきました。また、南海トラフ地震が発生する前には内陸の地震活動が活動的になるとして、阪神・淡路大震災をはじめとする内陸の活断層に関係する地震の発生と、南海トラフ地震発生の注意喚起をしていただきました。

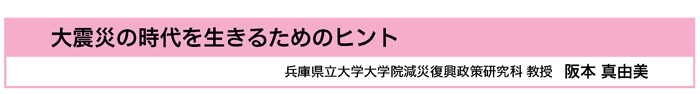
阪本教授は、「想定外」だった阪神・淡路大震災において、救助の方法、火災の対処、避難生活者の保護といった災害発生後の被害を防ぐ減災復興への備えがなかったことを課題として挙げました。防災に対処するマネジメント力やリテラシーといったヒューマンウェアの重要性を強調し、人と防災未来センターにおける実践的な防災人材の育成を紹介するとともに、能登半島地震での避難所生活の改善について紹介いただきました。また、アンケート結果により、住民の十分な備えがなされていない課題を提起し、「いつも」を「もしも」につなげるフェーズフリーの取組として、学校のフェーズフリー化や防災拠点型複合施設の設置、明石市ひなんサポーター研修といった取組を紹介いただきました。
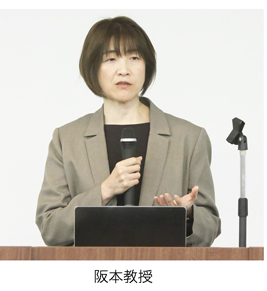

田利調整官からは、初めに阪神・淡路大震災当時に気象庁が発表した情報を時系列とともに解説いただいた後、震度観測点の増強や、震度計による震度観測の開始等、震災後に気象庁が実施した震度観測の改善により、命を守るための情報がより素早く詳細に発表できるようになったことを紹介いただきました。続いて、地震や津波の観測から緊急地震速報や津波警報・注意報などの発表までの流れや、緊急地震速報の仕組みを説明いただくとともに、そのような情報を見聞きした際の対処を解説いただきました。最後に、南海トラフ地震について、令和6年8月に話題になった南海トラフ地震臨時情報や南海トラフ地震関連解説情報を詳しく解説した上で、日頃からの地震への備えの重要性を強く呼びかけられました。

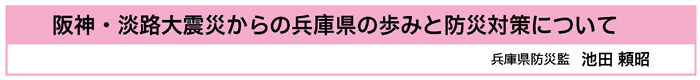
池田防災監からは、阪神・淡路大震災の教訓から、兵庫県が広域防災拠点の整備など災害に対する備え、消防団・自主防災組織の充実強化といった地域防災力の向上に取り組んできたことや、東日本大震災や能登半島地震における関西広域連合による被災地支援を例に、防災関係機関相互の連携を進めてきたことを紹介いただきました。また、南海トラフ地震と阪神・淡路大震災の特徴を比較した上で、南海トラフ地震・津波対策アクションプログラムに取り組んでいることや、能登半島地震を踏まえたひょうご災害対策検討会の取組や、令和6年から7年にかけて実施している阪神・淡路大震災30年事業の紹介をいただきました。最後に、防災意識の向上、自助・共助の強化による地域防災力の向上を地域住民に呼びかけられました。


本講演会は、吉野昌史神戸地方気象台長に閉会のご挨拶をいただき、盛況のうちに幕を閉じました。
オンライン視聴を含め、およそ150名が講演会に参加しました。会場では、地震や津波、防災に関するポスターなどの展示を行い、来場者が災害について学ぶことができました。また、来場者へのアンケートでは、阪神・淡路大震災における自助・共助からの学びや、南海トラフ地震への備えを意識する感想が寄せられ、災害に対する備えを見直すきっかけとなる講演会となりました。
地震本部では、地域講演会をはじめとするイベントを通して、引き続き地震本部の取組や成果の普及に努めていきます。

(広報誌「地震本部ニュース」令和6年(2024年)冬号)
スマートフォン版を表示中です。
パソコン版のウェブサイトを表示中です。